 かつて軍馬が駆け回った習志野原は、今では千葉県有数の商業地となっている
かつて軍馬が駆け回った習志野原は、今では千葉県有数の商業地となっている
「津田沼」という不思議な地名の由来
普段何気なく使っている「津田沼」という地名。この響きには、実は興味深い歴史が隠されています。
明治22年(1889年)、5つの村が合併して津田沼村が誕生した際、中核となった3つの村の名前から一文字ずつ取って命名されました。
- 谷津村の「津」
- 久々田村(菊田村)の「田」
- 鷺沼村の「沼」
このような「合成地名」は明治の大合併期によく見られましたが、津田沼ほど広く知られ、愛され続けている例は珍しいかもしれません。
江戸時代まで:小金牧と谷津田の世界
津田沼の歴史を語る上で欠かせないのが、江戸時代の「小金牧」の存在です。
現在の津田沼駅北側一帯は、徳川幕府の軍馬育成のための放牧場「小金牧」の一部でした。一方、南側の低地では「谷津田」と呼ばれる湿地の水田開発が行われ、農業を中心とした村々が形成されていました。
谷津、久々田、鷺沼の各村は、下総台地の浸食谷に開けた谷津田を基盤とする農村で、農業の傍ら東京湾での貝漁なども行っていました。
明治維新と「習志野原」の誕生

「習志野」の名は明治天皇によって命名された歴史的な地名
明治6年(1873年)、津田沼の歴史を大きく変える出来事が起こります。
小金牧の跡地の一部が陸軍の演習場となり、明治天皇によって「習志野原」と命名されたのです。この名前の由来には興味深いエピソードがあります。
陸軍大演習を視察した明治天皇が、篠原国幹陸軍少将の指揮ぶりを称賛し「篠原を見習うように」と述べたことから、「見習篠原」→「見習志野原」→「習志野原」に転じたと言われています。
軍都としての発展
明治時代後期から大正時代にかけて、津田沼周辺には次々と軍事施設が建設されました。
主要な軍事施設の変遷:
- 1896年(明治29年):高津廠舎(実籾)
- 1901年(明治34年):騎兵旅団(大久保)
- 1907年(明治40年):鉄道連隊第三大隊(津田沼)
- 1917年(大正6年):陸軍騎兵学校(薬園台)
- 1918年(大正7年):鉄道第二連隊
特に津田沼駅に隣接する谷津・久々田地区北部に鉄道連隊が転営すると、「津田沼」は鉄道連隊の町として全国に知られるようになりました。
行楽地としての一面
軍都として発展する一方で、津田沼には別の顔もありました。
大正期に台風被害で操業停止となった塩田の跡地には谷津遊園が開業。東京からの行楽客が潮干狩りや海水浴を楽しみに訪れ、津田沼は東京近郊の人気リゾート地としても名を馳せました。
また、谷津遊園から北側の台地部分は療養地や別荘地として開発が進み、モダンな住宅地の先駆けともなりました。
戦後の大転換:軍都から学園・住宅都市へ
昭和20年(1945年)の終戦とともに、津田沼は劇的な変化を遂げます。 広大な軍事施設の跡地は以下のように生まれ変わりました:
軍事施設から民間施設への転換:
- 学校用地:千葉工業大学、習志野市立第一中学校など
- 住宅地開発:現代的な住宅街の形成
- 工場用地:京成電鉄津田沼第二工場など
- 鉄道用地:新京成電鉄の路線(旧軍用鉄道の転用)
現在も残る「軍都の記憶」~新京成線の特異な線形

急カーブが続く新京成線は、鉄道連隊の訓練線の名残を今に伝えている
新京成線に乗ったことがある方なら、他の路線では体験できない急カーブの連続に驚いた経験があるのではないでしょうか。この独特な線形こそ、津田沼が軍都だった時代の貴重な遺産なのです。
新津田沼駅から松戸方面に向かう新京成線は、戦前の陸軍鉄道連隊が建設した軍用鉄道を転用したものです。鉄道連隊の兵士たちは、この路線で戦地での迅速な鉄道建設技術を習得していました。
軍用鉄道としての特徴:
- 速度よりも建設の迅速性を重視 – 戦場では素早く線路を敷設することが最優先
- 地形に合わせて柔軟に建設 – 大規模な土木工事を避け、自然の起伏に沿って敷設
- 実戦訓練としての意味 – 実際の戦地を想定した鉄道建設の練習
現在の新京成線の「くねくね」とした線形は、まさにこの訓練の名残です。鉄道連隊の兵士たちが「戦場で線路を作る時、早くできるように」と練習を重ねた証拠が、今でも私たちの日常の足となって活躍しているのです。
昭和29年:習志野市の誕生
昭和29年(1954年)、津田沼町と千葉市の一部が合併して習志野市が発足しました。
市名は、明治天皇によって命名された歴史的な「習志野原」に由来しています。「ならし」(訓練)の街でもあったことから、新しい市の名前として「習志野市」が選ばれたのです。
「津田沼戦争」~商業の街への華麗なる変身
1970年代から1980年代にかけて、津田沼は再び歴史の舞台となります。
この時期、津田沼駅周辺には大手流通各社の大型店が相次いで出店し、激しい競争を繰り広げました。当時のマスメディアはこの現象を「津田沼戦争」と名付けました。
津田沼戦争の主な出店状況:
- 1976年:長崎屋津田沼店
- 1977年:西武津田沼ショッピングセンター(パルコ・西友)、イトーヨーカドー津田沼店
- 1978年:丸井津田沼店、ダイエー、津田沼高島屋(サンペデック)
一つの駅周辺に全国区の大手流通業者が勢揃いする光景は「戦場にかける橋」(総武線上の橋と、かつてここにあった鉄道連隊をかけた洒落)などと表現され、話題となりました。
現代の津田沼:伝統と革新の共存
現在の津田沼は、千葉県でも有数の商業集積地として発展を続けています。
北口エリア:
- 津田沼パルコ(2023年閉店)、ミーナ津田沼
- イオンモール津田沼、イトーヨーカドー津田沼店
南口エリア:
- モリシア津田沼、Loharu津田沼
- 奏の杜フォルテ(新しい街「奏の杜」の核施設)
新しい街「奏の杜」の誕生
近年最も注目されるのが、津田沼駅南口に誕生した新しい街「奏の杜」です。
大規模な区画整理事業により、タワーマンションや戸建て住宅、新しい商業施設が建設され、津田沼の街並みは大きく変化しました。「奏の杜」という美しい名前には、新しい時代への期待が込められています。
文教都市としての側面
商業の街として有名な津田沼ですが、文教都市としての顔も持っています。
千葉工業大学津田沼キャンパスをはじめとする教育機関が多数立地し、多くの学生が行き交う学園都市でもあります。学習塾業界を描いた小説『みかづき』の舞台としても知られ、教育への関心の高い街として認識されています。
伝統文化の継承
現代的な発展を遂げる一方で、津田沼周辺では伝統文化も大切に継承されています。
習志野市には千葉県指定無形民俗文化財である「下総三山の七年祭り」などの伝統的な祭事が受け継がれており、新旧の文化が共存する独特の魅力を醸し出しています。
交通の要衝としての発展
津田沼の発展を語る上で欠かせないのが、交通の便利さです。
現在の津田沼駅周辺の交通網:
- JR総武線(快速・各駅停車)津田沼駅
- 京成本線・松戸線・千葉線 京成津田沼駅
- 京成松戸線 新津田沼駅
- 京成本線 谷津駅
これらの駅が半径2km圏内に密集し、東京方面、千葉方面、松戸方面への交通の要衝となっています。
津田沼が歩んできた150年
津田沼の歴史を振り返ると、この地域がいかに時代の変化に適応し、発展し続けてきたかが分かります。
津田沼の変遷:
- 農村時代:江戸時代の谷津田と小金牧
- 軍都時代:明治~昭和の軍事都市
- 復興・発展時代:戦後の学園・住宅都市化
- 商業都市時代:「津田沼戦争」による商業集積
- 現代:商業・文教・住宅の複合都市
未来への展望
現在の津田沼は、長い歴史の中で培われた多様な魅力を併せ持つ街となっています。
商業施設の充実、教育環境の良さ、交通の便利さ、そして新しい街「奏の杜」の誕生。これらすべてが、津田沼の豊かな歴史の上に築かれているのです。
まとめ:歴史を知ると街がもっと面白くなる
津田沼駅の電光掲示板で「津田沼」の文字を見かけた時、そこには150年以上にわたる豊かな歴史が込められていることを思い出してみてください。
軍馬が駆け回った習志野原、鉄道連隊の兵士たちが訓練を重ねた土地、東京からの行楽客で賑わった谷津遊園、激しい商業競争が繰り広げられた「津田沼戦争」の舞台…
これらすべての歴史が重なり合って、現在の津田沼があるのです。
JR津田沼駅開業130周年記念
そして今年、JR津田沼駅は開業130周年という記念すべき年を迎えています。9月21日には記念イベントが開催され、多くの人々がこの歴史ある駅の節目を祝います。
明治27年(1894年)に開業したJR津田沼駅は、軍都としての津田沼、商業都市としての津田沼、そして現代の津田沼まで、すべての時代の発展を見守り続けてきた「街の証人」とも言える存在です。
歴史を味わう特別メニュー

この記念すべき年に、地元のお好み焼き・もんじゃ焼き店「粉と水」では、JR津田沼駅開業130周年記念メニューを発売中です。長い歴史を持つ津田沼の街で、新しい味の歴史を刻んでみませんか?
歴史を知ることで、いつもの街並みがもっと興味深く、愛着の湧く場所に変わるかもしれません。津田沼は、そんな発見に満ちた街なのです。
津田沼の歴史は、日本の近現代史の縮図でもあります。
この街を歩くたびに、時代を超えた人々の営みを感じてみてください。
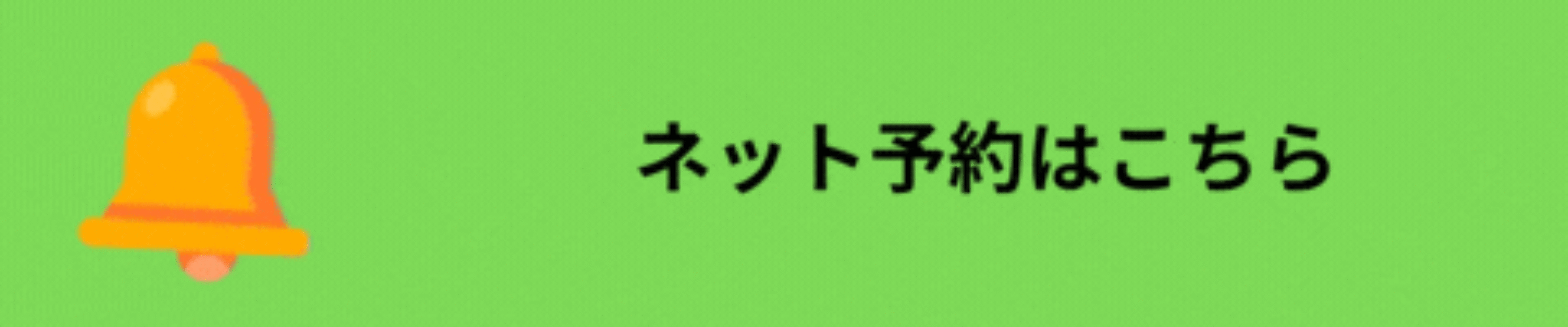



コメント